【入力情報】
キーワード:[仰せ コールセンター]
記事テーマ:[コールセンターで「仰せ」は使うべき?お客様対応での適切な敬語表現]
記事タイトル:[仰せ コールセンター敬語初心者にありがちな間違い5選と落とし穴]
仰せ コールセンター敬語初心者にありがちな間違い5選と落とし穴
「仰せ コールセンター」という検索をする方は、お客様対応でこの言葉を使っていいのか悩んでいるのではないでしょうか。
敬語として一見丁寧に思える「仰せ」ですが、実はコールセンターの現場では使用を避けたほうがよい敬語表現のひとつなんです。
本記事では、新人オペレーターや未経験者が陥りやすい誤用パターンをわかりやすく紹介しながら、適切な敬語選びのポイントを具体例と共に解説していきます。
さらに、コールセンター歴10年の筆者「成瀬 彩(あやち)」の現場体験も交えて、実際にあった失敗例や新人教育の中で教えている現場感覚まで包み隠さずお伝えします。
「正しい敬語」を使うことは、単にマナーの問題ではなく、お客様との信頼関係を築く第一歩なんですよ。
「仰せ」は本当に必要なのか? それとも避けるべきか? 迷っている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
仰せ コールセンターでの使用はNG!敬語としては不自然で誤解を招く
「仰せ」は現代の電話対応に適さない
「仰せ」は確かに丁寧な日本語であり、古くから使われてきた格式ある表現です。
しかしながら、現在のビジネス電話応対においては「時代錯誤」「過剰に堅苦しい」といった印象を与えてしまうことが多く、現場ではあまり推奨されていません。
とくにコールセンターのようにスピーディかつ明確なやり取りが求められる場面では、回りくどい言い回しは逆に混乱や違和感を生むことがあるんです。
お客様から違和感を持たれるリスクが高い
たとえば「仰せの通りにいたします」と返答した場合、一部のお客様には過剰なへりくだりや不自然さが伝わってしまいます。
その結果、「マニュアル感が強くて機械的」「本当に伝わっているのか不安」といったネガティブな印象を与えてしまうケースも少なくありません。
特に高齢の方やビジネスマナーに敏感な層にとっては、「妙に丁寧すぎてかえって失礼」と感じられるリスクすらあるんですよ。
正しい敬語を使うことで信頼感が生まれる
逆に、「承知いたしました」「かしこまりました」など現場で一般的に使われている敬語を的確に使うことで、お客様の安心感や信頼を得ることができます。
敬語に必要なのは”格式”よりも”自然さと聞き取りやすさ”なんです。言葉の丁寧さではなく、「伝わるかどうか」「不快感を与えないか」が最も大切なポイントになります。
意味だけを追って形式的な言葉を選んでしまうと、かえって心が通わない対応になりがちです。
したがって、「仰せ」はコールセンター業務においては避け、現代のビジネスマナーに即した敬語を選ぶことが重要なんですね。

新人の頃、とある業界で「仰せの通りに承ります」とお客様にお伝えしたことがあって……。
一瞬間があってから、「あの、仰せって…今どき使うんですか?」ってちょっと笑われてしまったんです。
丁寧なつもりで使ったのに、逆に違和感を持たれてしまって。それ以来、言葉の「格式」より「伝わりやすさ」を意識するようになりました。
なぜ「仰せ」が不適切なのか?敬語の原則から見る理由
古風で堅すぎる表現になりやすい
「仰せ」という言葉は、文語的で非常に古風な印象を持ちます。
ビジネス会話、とくに電話応対のような口語表現の場では、あまりに堅すぎる言い回しは不自然に響くことが多く、相手との距離を生んでしまうことがあるんです。
実際にお客様対応では、「そんな堅い表現より、普通に言ってもらった方がわかりやすい」という反応も少なくありません。
そのため、“丁寧=伝わる”とは限らないという認識を持つことがとても大切です。
「仰せ」は上司や目上の人への使用が基本
敬語の本来の使い方として、「仰せ」は上位者からの命令やご指示に対して用いられる言葉です。
たとえば、「社長の仰せの通りにいたします」というように、相手を”かなり上の立場”と見なす言葉として使うのが基本となります。
ところが、コールセンターでは「対等かつ丁寧なコミュニケーション」が求められるため、「仰せ」を使うことで過剰にへりくだったり、不自然な上下関係が生まれてしまうリスクがあるんです。
その結果、お客様が「本心ではそう思ってないのでは?」と警戒心を抱く可能性もあるため、使い方には慎重になる必要があります。
ビジネスマナーでは「違和感のない言葉」が最優先
コールセンターの研修やマニュアルで指導される敬語は、何よりも「自然さ」と「聞き取りやすさ」を重視しています。
相手に理解されやすく、感情的なストレスを与えない表現こそが、現代のビジネスマナーにおける”正しい敬語”なんですね。
そのため、いくら丁寧でも「仰せ」のように格式が高すぎる言葉は、むしろ避けられる傾向にあります。
このように、「言葉の印象」が与える影響は、内容そのもの以上に大きな意味を持つんです。
.jpg)
数年前、新人スタッフ向けの研修を担当したとき、「仰せ」という言葉を覚えたばかりの子がいて。
一生懸命丁寧に対応しようと「お客様の仰せの通りに…」と話したんですが、受電後に先輩から「それ、ちょっと違和感あるね」と言われて。
そのとき、いくら丁寧でも”お客様にとって自然じゃない表現”は避けるべきだなと、改めて感じた瞬間でした。
実際にあった!仰せ使用によるトラブルと自然な言い換え例
「仰せの通りに」は上から目線と誤解される可能性
ある女性オペレーターが、お客様からの依頼に対して「仰せの通りに対応いたします」と返答したところ、相手から「なんだか上から目線に感じるね」と言われてしまった事例があります。
本人としては丁寧に返しているつもりでしたが、「仰せ」という言葉が持つ”特別感”や”格式の高さ”が、相手に構えた印象を与えてしまったんですね。
特に感情的になっているお客様に対しては、言葉選びひとつで信頼関係が崩れてしまうこともあるため、慎重さが求められます。
「承りました」「かしこまりました」への置き換えが基本
研修やマニュアルでも、こうした誤解を避けるために「承知いたしました」「かしこまりました」といった表現が基本として教えられています。
たとえば「ご変更の件、仰せの通りに承ります」ではなく、「ご変更の件、かしこまりました」とすることで、違和感なくスムーズに話が進みます。
丁寧にしようとするあまりに回りくどくなってしまうよりも、簡潔で正確な敬語を使う方が、お客様にとっては好印象につながるんです。
コールセンターの研修でも「仰せ」は使わないケースが多数
実際に多くのコールセンター現場では、「仰せ」はNGワードに近い扱いをされているケースが多々あります。
たとえば、私の以前の職場でも、新人が「仰せの通りに…」と話した際、先輩スタッフがすかさず「それは使わないように」と注意をしていました。
その理由としては、「仰せ」を使うと”本心では従っていないのでは”と受け取られる可能性があるからなんです。
このような経緯から、実用性のある敬語表現が優先されるのが、現場での共通認識となっています。
では、なぜそこまで「仰せ」が避けられるのか?次のセクションでは、その背景にある意識や対応の原則を再確認していきましょう。

新人スタッフが「仰せの通りに承ります」と言いかけたとき、「うん、それ、ちょっとやめとこっか」とやんわり止めたことがありました。
本人は一生懸命覚えた敬語を使いたかったようなんですけど、「お客様にどう伝わるか」を基準に考えるよう伝えました。
言葉って、意味だけじゃなくて”響き”や”温度感”が大事なんですよね。
結論:仰せ コールセンターでは使わず自然な敬語を徹底しよう

お客様に安心感を与える表現が最優先
コールセンターの現場で最も重視されるのは、言葉の格式ではなく「伝わりやすさ」と「安心感」です。
「仰せ」といった堅い表現よりも、「かしこまりました」「承知いたしました」など、現場でよく使われる自然な敬語の方が、スムーズなやりとりにつながります。
お客様の立場からしても、あまりにかしこまりすぎた言葉よりも、誠意が伝わるわかりやすい言葉のほうが好印象なんです。
「仰せ」に頼らず正しい敬語を身につけるべき
新人のうちは「丁寧な言葉」を意識するあまり、格式の高い表現に頼りがちですが、それが誤解を招くこともあります。
敬語とは、お客様の立場を尊重しつつ、誤解やストレスを生まない伝え方が求められるんですね。
「仰せ」のように使い慣れない表現は避け、定着しているビジネス敬語を正確に使えるようになることが、対応品質の向上につながります。
対応品質は敬語の正確さで大きく変わる
ちょっとした言葉選びで、お客様の印象は大きく変わります。
特に電話対応では、表情が見えない分、言葉のトーンや言い回しが信頼感を生む鍵になるんです。
だからこそ、「仰せ」のように場に合わない表現は避け、丁寧で正確な言葉を使う姿勢が求められるんですよ。
では次に、こうした「仰せ」のような敬語をなぜ人は使いたくなるのか、そしてどう対処していくべきかを考えていきましょう。
仰せのような「使いたくなる敬語」ほど注意が必要
丁寧に見える言葉ほど誤解されやすい落とし穴
「仰せ」のような古風で丁寧な言葉は、敬語を覚え始めたばかりの新人にとって、つい使ってみたくなる響きがありますよね。
しかし、その「丁寧に見える」言葉こそが、実は誤解されやすく、信頼を損なう原因になりかねないことは意外と知られていません。
たとえば、「仰せの通りに」と言われたときに、温かさや誠実さを感じる方は多くないんです。
形式よりも心が伝わる言葉こそが、現場で必要とされている「本当の丁寧さ」なんですよ。
現場での使い分け力がコールセンターの評価を左右する
一見正しくても、使う場面や相手によっては逆効果になる言葉があります。
たとえば、クレーム対応中に「仰せの通りに…」と返すと、かえって皮肉に聞こえる可能性すらあるんです。
そのため、コールセンターの品質評価は、内容よりも”伝え方”や”温度感”によって左右されるといっても過言ではありません。
言葉の選び方は、単に正しいかどうかだけでなく、“相手にどう受け取られるか”を常に意識して判断する必要があります。
新人教育では「敬語の引き算」の発想が重要
新人のうちは「丁寧さ=敬語をたくさん使うこと」と考えがちです。
しかし、現場で求められるのは「必要な敬語だけを残す」という、いわば“敬語の引き算”の考え方なんです。
「仰せ」などの過剰な敬語は、丁寧さよりも違和感を残してしまうため、指導現場では積極的に排除されることが多いんですよ。
伝える力とは、難しい言葉を知っていることではなく、わかりやすく、自然な言葉で相手に届くかどうかにあるんです。
では最後に、本記事のポイントをまとめつつ、読者の方からよくある質問についても補足していきましょう。

あるとき、新人の子が「仰せのような丁寧な言葉をいっぱい使わなきゃ」と頑張っていて。
「気持ちは素晴らしいけど、丁寧さって”言葉の格”じゃなくて”伝え方の優しさ”なんだよ」と伝えました。
それからはその子、表情も声のトーンもずっとやわらかくなって、電話もぐんとスムーズになったんです。
まとめ
「仰せ コールセンター」で検索する方の多くは、「この表現は正しいのか?」「お客様に失礼にならないか?」といった不安を抱えていることでしょう。
この記事では、「仰せ」が現代のコールセンターにおいて不自然かつ誤解を招きやすい表現であることを、理由や具体例とともに解説してきました。
敬語は「丁寧さ」よりも、「自然さ」と「安心感」を重視すべきなんです。
“正しく伝わる敬語”を選ぶことで、対応品質は確実に向上します。
また、潜在的な本音として、「マニュアル通りの対応では信頼されない」「形式ではなく心が伝わる言葉が必要」といった気持ちに対しても、本記事は実践的な視点から具体的な答えをお届けしました。
これから敬語を学び始める方も、現場での対応に悩んでいる方も、「仰せ」のような一見丁寧な表現に惑わされず、本当にお客様に伝わる敬語を身につけていきましょう。
よくある質問(Q&A)BEST3
Q. 「仰せの通りに承ります」は本当に失礼なんですか?
失礼というより、「過剰すぎて不自然」と受け取られることが多いんです。現代のビジネス現場では、「かしこまりました」「承知いたしました」などがスタンダードですので、違和感のない表現を選ぶほうが望ましいでしょう。
Q. 研修で「仰せ」は出てこなかったのですが、それでも覚えた方が良いですか?
基本的には覚える必要はないんですよ。むしろ、研修で教えられていない敬語を無理に使うと混乱や誤用の原因になります。
「仰せ」は書き言葉や式典など、特殊な場面での使用に限られますので、普段の電話応対では避けた方が無難です。
Q. 「仰せ」ではなくて、少し丁寧な表現を使いたいときはどうすればいいですか?
「かしこまりました」より丁寧にしたい場合は、「恐れ入りますが」「念のため確認させていただきます」といった前置き表現を加えるのがおすすめです。
過剰に格式ばるのではなく、聞き手に配慮する言い回しを増やすことが自然な丁寧さにつながります。
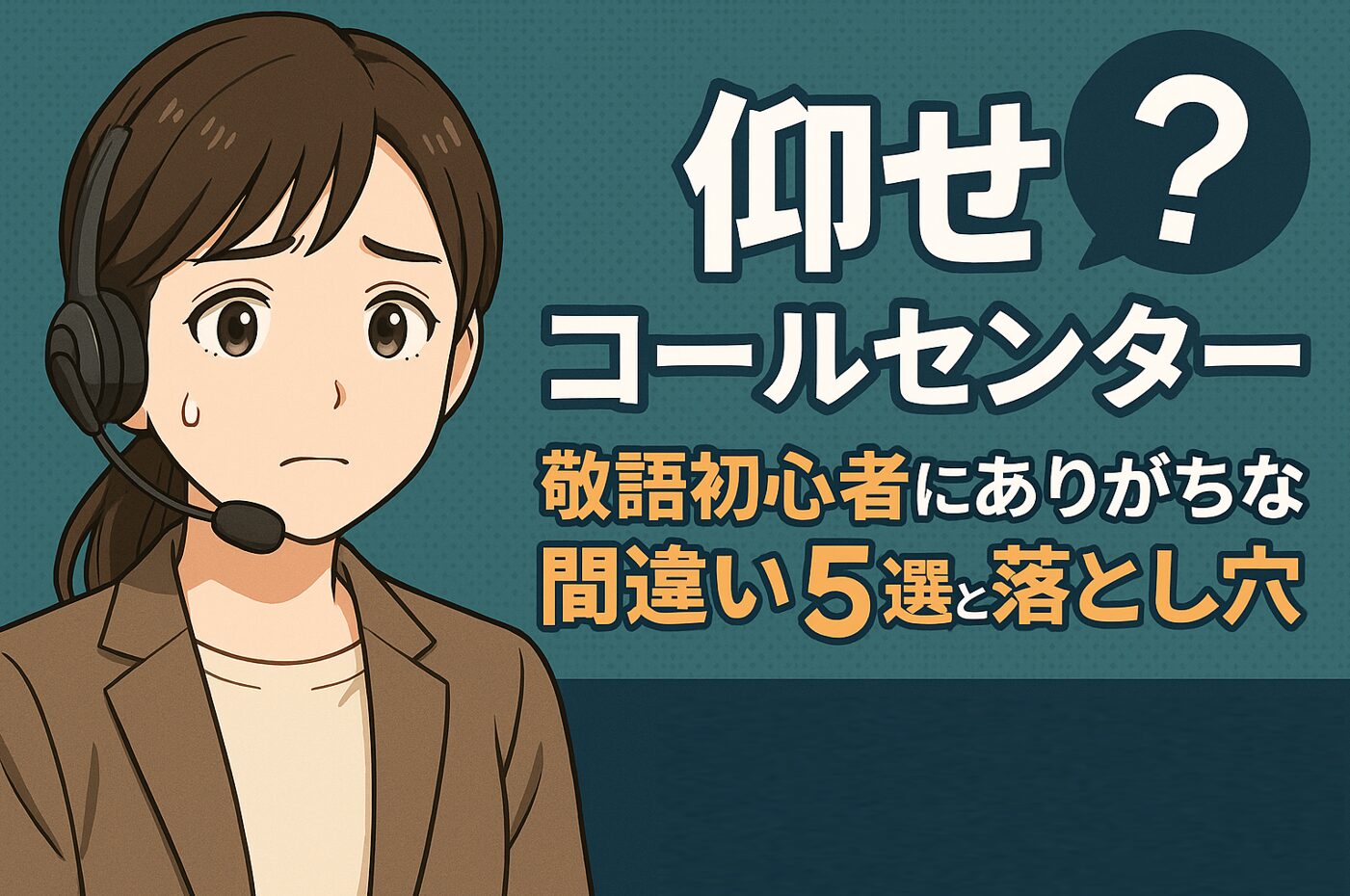


コメント